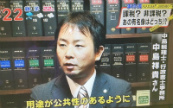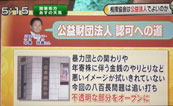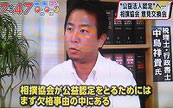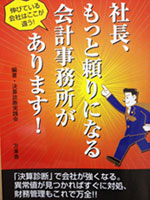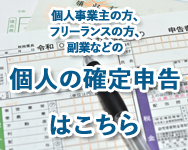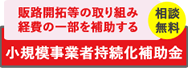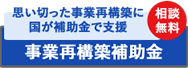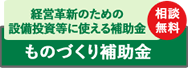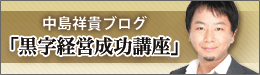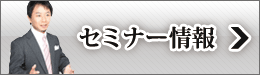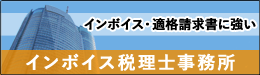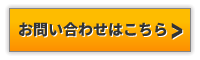Posts Tagged ‘課税’
2015-03-23
遺族が支払を受ける年金に対する課税上の扱い【源泉所得税】
Q. 私の夫は昨年死亡しました。その後、夫には一昨年の中途から厚生年金(老齢年金)の受給資格があったことを知りました。 そこで私が、私の名において年金の請求をすることにしましたが、裁定を受けた後に私が給付を受ける年金に […]2014-02-28
食事の現物給与の取扱いとその評価【源泉所得税節税】
Q.当社では、従業員に毎日昼食を支給していますが、この食事の現物給与の取扱いについて説明してください。 A.使用者が従業員に対して支給する食事(残業又は宿日直をした人に支給する食事を除きます。)については、次により取り扱 […]2014-02-14
永年勤続者に支給する表彰記念品【源泉所得税節税】
Q. 当社では毎年、勤続5年、10年、15年、20年及び25年に達した社員に対し、5万円相当の記念品を支給するこしていますが、給与として課税の対象としなければなりませんか。 また、この記念品に代えて金銭を支給することと […]2014-02-04
社用車を通勤用に使用する場合の取扱い【源泉所得税節税】
Q.当社は、営業社員には業務のために社用車を使用させていますが、社員が自宅から直接得意先等へ行くことがよくありますので、社用車で通勤させています。 この場合の、社用車を利用することによる経済的利益は、給与として課税され […]2014-01-30
障害補償を増額支給した場合【源泉所得税節税】
Q.労働基準法の規定により支給する障害補償は、所得税が課されないことになっていますが、当社では労使協定により同条に規定する金額を超えて支給することにしています。 法定額を超えて支給するものは当社の内規では「障害特別補償 […]2014-01-21
藍綬褒章を授与された役員に支給する祝金【源泉所得税節税】
Q.当社の会長は、この度、業界の発展に関しその功績が著しかったことにより藍綬褒章を授与されました。 そこで、当社においても、この受賞祝金として現金50万円を支給することになりました。 この祝金の支給について、課税する […]2014-01-20
勤務成績の優良な社員に支給する表彰金【源泉所得税節税】
Q.タクシー業を営む当社では、内規により表彰制度を設け、毎年1回、次に該当する社員を表彰し、それぞれの賞金を支給していますが、給与として課税しなければなりませんか。 (1)無事故運転表彰・・・賞金 3万円 (2)無欠 […]2013-07-05
運転免許証の更新費用 【所得源泉税節税】
Q117 当社では自動車販売業を営んでいます。営業部門の社員は全員、自動車の運転免許を必須としているため、免許を持っていない社員には取得費用を会社で負担しています。 営業部門の社員に対し、自動車の運転免許証の更新費用も […]2013-06-19
職員への制服支給 【源泉所得税節税】
Q106 当社では、一般の事務職員に制服を支給し、就業中は必ず着用しなければならないこととしています。この制服については、現物給与として課税の対象としなければなりませんか? A106 給与所得者でその職務の性質上、制服を […]2013-06-13


 ダウンロードはこちら
ダウンロードはこちら